① 導入
学級経営の中で「毎回同じことを注意している」「ルールはあるけれどなかなか浸透しない」と悩んだことはありませんか?
私自身も、子どもたちにどう学んでほしいか・どう生活してほしいかをうまく伝えられず、気がつけば注意ばかりしてしまう時期がありました。
そこで取り入れたのが 「学習・生活スタンダード」 です。
これは「叱るためのルール」ではなく、学年末に目指す理想の姿を言葉にしたもの。
私はこのスタンダードを 週案ノートに挟んで、学級経営の軸 として活用しています。
毎週の予定を整理するのと同じように、学級全体の方向性をスタンダードとして見える形にしておくことで、先生自身も子どもたちも安心して過ごせるようになりました。
② 学習・生活スタンダードとは?
学習・生活スタンダードとは、学校や学級の細かいルールとは違い、**その学年が終わるときに目指す「理想の姿」や「学年相応のマナー」**を示したものです。
たとえば、
-
ノートの書き方
-
発表や話し合いの仕方
-
あいさつや廊下での過ごし方
といった場面ごとに、子どもたちと共通理解をもって取り組むための「指針」となります。
大切なのは、守れていなくても叱るのではなく、理想に向けて「一緒にがんばろう」と声をかけること。
学級に掲示しておき、できている子を見つけて褒めることで、少しずつクラス全体に浸透していきます。
このスタンダードは、教師理念(理想の教師像や子どもの姿)に基づいて考えると一貫性が出ます。
※教師理念については、次回の記事で詳しく解説します。
③ 学習・生活スタンダードの意義
スタンダードを設定することで、次の3つの効果があります。
-
子どもにとって:「どうすればいいか」が明確になり、安心して学習や生活に取り組める。
-
教師にとって:毎回同じ注意を繰り返す必要が減り、心の余裕が生まれる。
-
学級全体にとって:共通の目標を共有することで、一体感が生まれる。
私は、週案ノートで「自分のタスクを整理して見える化」しているのと同じように、スタンダードを「子どもの行動の見える化」として位置づけています。
どちらも、仕組みを整えることで余裕を生み出す工夫なのです。
④ 学習・生活スタンダードを作るための5つの質問
スタンダードを作るときは、次の5つの問いを自分に投げかけてみると整理しやすいです。
-
子どもに守ってほしいことは?
-
先生が褒めたくなるような行動とは?
-
子どもや先生、保護者の負担を減らす行動とは?
-
先生として、ここだけは譲れないことは?
-
社会に出たときにできるようになってほしいことは?
これらを考えて書き出すと、自然と自分の学級に合ったスタンダードが浮かび上がってきます。
⑤ 実際の学習・生活スタンダードの例
私が実際に掲示しているものをいくつか紹介します。
-
学習面
「ノートは読める字で丁寧に書こう」
「忘れ物をした時はそのままにせず、連絡帳に書いてから先生に言おう」
-
生活面
「廊下は静かに歩こう。机の上を片付けてから椅子をしまって移動しよう。」
「あいさつは目を見て元気にしよう」
ポイントは、表記を『〜しない』ではなく『〜しよう』とポジティブに書くこと。
運用の工夫(補足)
私はこのスタンダードを、学級掲示と週案ノートの両方に置いています。
毎朝週案ノートを開くときにスタンダードにも目を通すことで、子どもへの声かけの軸がぶれないようにしています。
授業中には「今日はこのスタンダードを意識してみよう」と伝えたり、できたときに「スタンダード通りにできたね」と褒めたりしています。
スタンダードは「注意するため」ではなく、「褒める材料」として活用するのがポイントです。
⑥ ダウンロードして使えるフォーマット
今回紹介した「学習・生活スタンダード」のフォーマットを配布します。
ワークシート形式になっているので、自分の学級に合わせて自由にアレンジして使ってください。
私はこれを 週案ノートに挟んで、日々の学級経営の軸 としています。
⑦ まとめ
学習・生活スタンダードは「叱るためのルール」ではなく、先生と子どもが一緒に目指す姿を共有する仕組みです。
週案ノートで先生自身のタスクを整理するように、スタンダードは子どもの学びや生活を整理します。
どちらも「仕組みで余裕をつくる工夫」であり、先生の働き方を支えてくれます。
まずは配布シートを使って、自分の学級のスタンダードを考えてみてください。
次回は、このスタンダードづくりの土台となる 「教師理念の作り方」 を詳しく解説していきます。ここまで読んでいただいてありがとうございました。
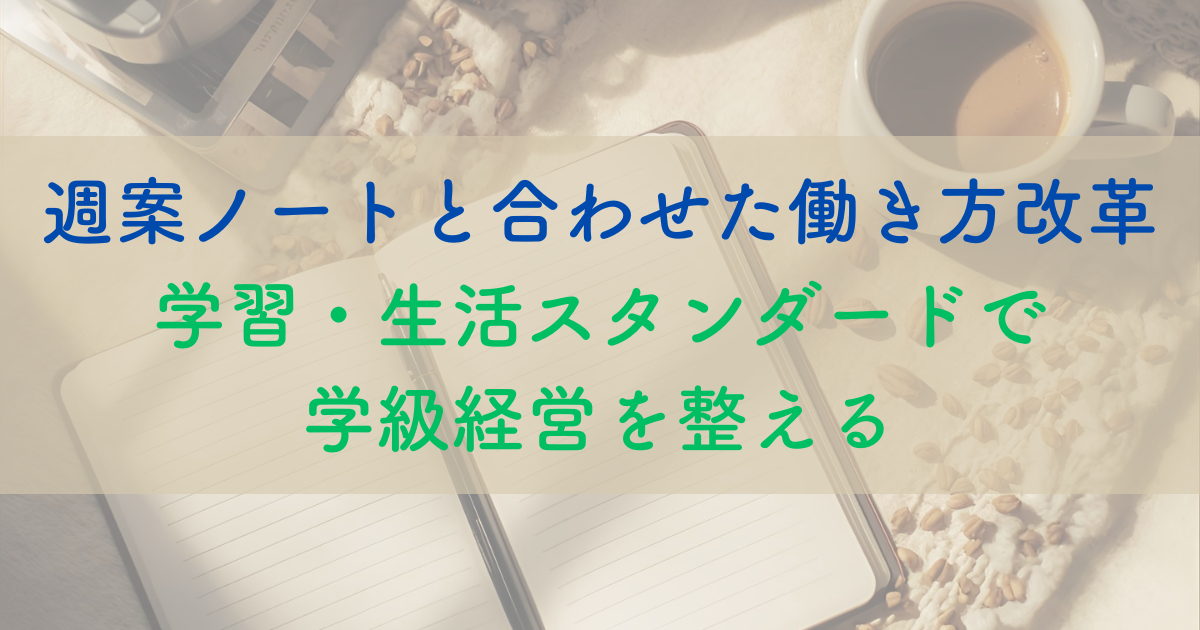
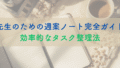
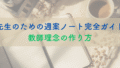
コメント