こんにちは、「ライフワークゼミ」です。
今日は、私が定時退勤を叶えるために取り入れた週案ノートについてご紹介します。
こんな悩みありませんか?
「今日って、何をどこまでやるんだっけ…?」
毎朝職員室で、そんなふうに机の前でフリーズしていませんか?
私もかつて、やるべき仕事が頭の中でグルグルして、気がつけば定時を大きく過ぎて退勤…そんな日々でした。
一生懸命に仕事を進めているのに、丸つけや雑務、急な生徒指導対応と、次々に仕事は降ってきて、計画通りに進まない。
でも今は、自作の週案ノートを使うことで、毎朝の迷いもなくなり、仕事のペースが掴めるようになりました。
やるべきことを「見える化」するだけで変わる
結論から言うと、「やるべきことを可視化し、定期的に見直す」だけで、仕事の優先順位が明確になり、落ち着いて1日をスタートできるようになります。
私は自作の週案ノートを、次の3ステップで活用しています。
私の週案ノート3ステップ
-
月曜日は、先週金曜に作成したリストを見返して追記や修正
-
毎朝、タスクリストを確認し、その日の目標や優先順位を明確化
-
金曜日に、2週間分のリストをバレットジャーナル形式で作成(授業計画・会議予定・タスクを箇条書き)
このサイクルを習慣化することで、仕事に追われる感覚が減り、落ち着いて定時退勤できるようになりました。
週案ノートを始める前と後でこんなに違った
教師3年目のころまで、私はその場しのぎで毎日の仕事を回していました。
少しずつ仕事には慣れてきたものの、校務分掌の内容は年々重くなり、学年や委員会だけでなく、学校全体に関わる責任も増えていきました。
授業そのものは楽しかったのですが、放課後になると会議、書類作成、事務作業…と仕事の山に追われる毎日。
家に帰っても、晩ごはんを食べてお風呂に入ったら、もう寝るだけ。教材研究も、自分のリフレッシュも後回しになっていました。
気づけば、子どもたちに対しても、以前のように余裕を持って接することができなくなっていたのです。
「このままではいけない」と思った私は、まずは自分の時間と仕事の全体像を整理しようと、自作の週案ノートを作ることにしました。
すると、仕事の見通しが立ち、「今日やるべきこと」と「今週中でいいこと」の区別ができるように。
日々の迷いが減ったことで、自然と放課後の時間の使い方にもゆとりが生まれ、子どもにも、そして自分にも優しくなれた気がしています。
週案ノートの使い方と構成
ここからは、私が実際に使っている「週案ノート」の書き方をご紹介します。
ポイントは、“見通しを立てること”と“シンプルに書けること”。続けやすさを重視して作りました。
書き方の流れ(3ステップ)
-
月曜日:先週金曜日のリストを見返して追記・修正
-
毎朝:その日のタスクを再確認し、優先順位を明確化
-
金曜日:2週間分の予定をリスト化して準備
ノート構成(A4見開き・1週間)
|
左ページ(自分用) |
右ページ(子ども配布) |
|---|---|
|
・目標管理(授業・児童・校務) ・リスト(授業準備・会議予定・タスク) ・振り返り欄 |
・時間割・行事予定・持ち物など |
💡書き込みすぎず、あくまで「見える化」と「見通し」が目的です。
💡完璧を目指さず、メモ的に書くのが長続きのコツです。
無料PDFサンプルを配布中!
今回紹介した週案ノートのフォーマット(記入例付きPDF)を無料で配布しています。
ご自身のスタイルに合わせて自由にカスタマイズしてご利用ください。
👉 ダウンロードはこちら:週案ノートPDF
※バレット記号や書き方の詳細は次回以降の記事で詳しく解説します!
今すぐできる!ちょっとした一歩
忙しい先生ほど、「全体を見渡す時間」がなかなか取れないものです。
でも、自分の仕事の見通しが持てるだけで、1週間の過ごし方は大きく変わります。
まずは、自分の手帳やメモに「来週の予定」をざっくり書き出してみるだけでもOKです。
PDFもぜひ活用してみてくださいね。
使ってみた感想をぜひコメント欄でお聞かせください。
書き方やバレット記号の使い方は次回のブログで詳しく解説予定です。
「もっと早く知りたい!」という先生は、インスタグラム(@soy_latte24)で記入例なども公開していますので、ぜひご覧ください!


おわりに
忙しい日々の中でも、「どうしたら自分の時間を取り戻せるか」を考えることは、決してわがままではありません。
先生が少しでも心に余裕を持てるようになれば、そのあたたかさはきっと子どもたちにも伝わっていきます。
次回は、週案ノートのバレット記号や書き方のコツをご紹介します。
「ライフワークゼミ」では、先生たちがもっと気軽に働ける環境づくりや、時間と心にゆとりを生むための実践アイデアを発信中です。
今後も、あなたらしい働き方を見つけるヒントをお届けしていきます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
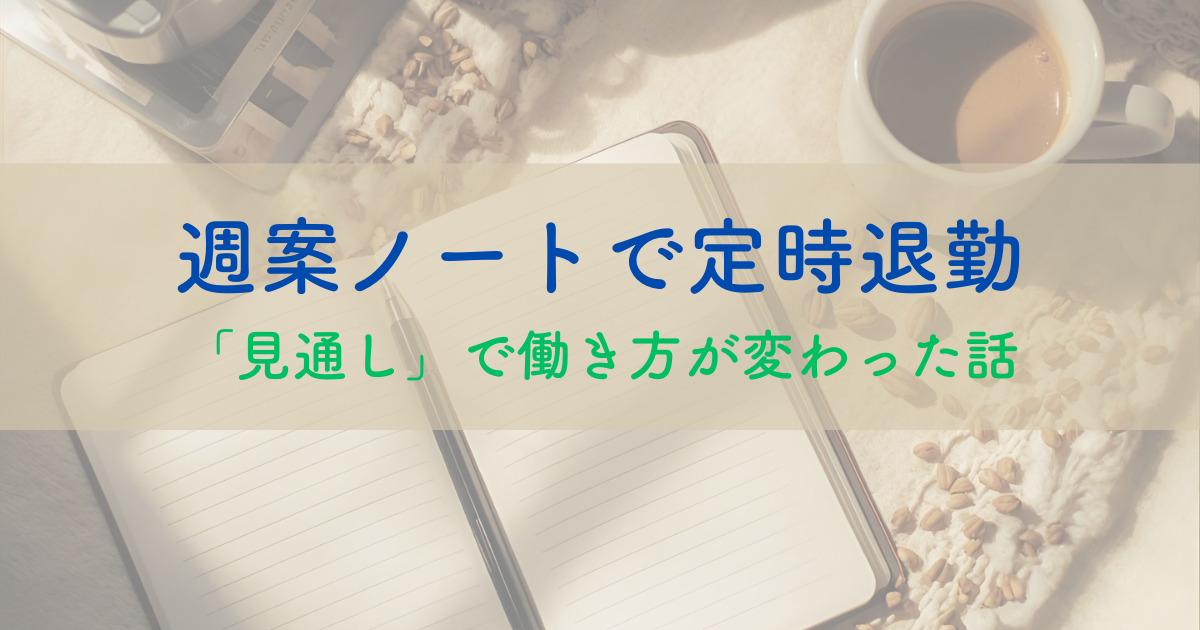
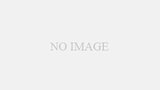
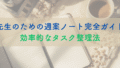
コメント