「戦略なき」学級経営は、先生を消耗させる
「学級経営は戦略だ」と言われても、あまりピンとこない先生もいるかもしれません。
戦略を意識せずに担任を続けているとしましょう。
どうしても毎日が「行き当たりばったり」になってしまいます。
朝から授業、休み時間にはトラブル対応、放課後は会議と事務作業…。
気づけば夜になり、「今日も計画通りに進まなかった」と肩を落とす日々。
気合と根性で走り切っても、疲れがたまるばかり。
先生の余裕も子どもの安心も生まれません。
学級経営は「頑張ればなんとかなる」ものではありません。
場当たり的に対応するほど、定時退勤は遠ざかり、先生自身が消耗してしまいます。
なぜ「戦略」が必要なのか
学級経営を持続可能にするためには「戦略」が欠かせません。
ここでいう戦略とは「1年をどういう流れで進めるか」という全体設計のことです。
戦略があると、日々の判断がシンプルになります。
例えば、子どものトラブル対応をするときのことを考えてみましょう。
「今学期の目標は“挑戦”だから、この経験を挑戦につなげよう」と考えられる。
行事の計画を立てるときも、「2学期は“協働”がテーマだから、子どもたちに役割を分担してやらせてみよう」と判断できる。
戦略があるだけで、迷いが減り、判断がぶれなくなります。
そして、先生が安心して動けると、子どもたちにも自然と安心感が広がっていきます。
実際の学級経営案(実物紹介)
こちらが、私が実際に使っている学級経営案です。
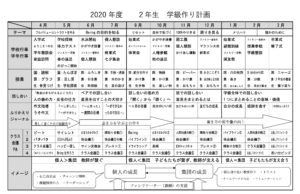
1年間の大きな行事、学期ごとの目標、そして学級活動の柱を1枚に整理しています。
こうして一目でわかるようにしておくと、迷ったときに立ち返れる“地図”になります。
例えば、秋に運動会を控えているとき。
経営案を見返すと「2学期=挑戦」という軸があるので、「子どもたちが挑戦できるように、役割を任せよう」と判断できる。
あるいは、授業中に落ち着かない子がいたときも、「1学期=安心」がテーマだから、安心感を与える対応を優先しよう、と動けます。
戦略を「見える形」にしておくことが、担任を助ける大きな力になるのです。
学期目標が学級経営の軸になる
戦略の中心にあるのは「学期目標」です。
「1学期=安心」「2学期=挑戦」「3学期=感謝」など、たった一言で構いません。
この学期目標を立てておくと、活動全体が一つにまとまります。
例えば、「挑戦」がテーマの2学期であれば、運動会では役割分担を工夫する。
算数ではちょっと難しい課題に挑戦させる。
行事も学習も、目標の方向にそろっていくのです。
実際、多くの先生は学期目標を立てずに進めています。
毎日の授業や行事に追われると「その日をどう回すか」で手一杯になり、中期的な目標を意識する余裕がなくなってしまうからです。
だからこそ、学期目標を設定すること自体が、学級経営を戦略的に進める第一歩になります。
学級経営案の作り方(概要)
「学級経営案をつくる」と聞くと難しく感じるかもしれません。
ですが、完璧である必要はありません。
大切なのは「担任としての地図を持つこと」です。
大まかな流れは次のとおりです。
- 学級の柱になる言葉を書く(どんなクラスにしたいか)
- 年間行事を整理し、節目ごとに意識する力を決める
-
学期ごとの目標を一言で決める(例:安心・挑戦・感謝)
-
コア活動を1つ決める(振り返りジャーナル、クラス会議など)
このように、シンプルにまとめるだけでも十分です。
詳細なステップや実例は次回の記事で解説します。
まとめ
学級経営案を書くのは、最初は時間がかかります。
けれど、その時間をかける価値は大きいです。
小さな準備が、先生の余裕と子どもの安心を支えます。
まずは一言でも構いません。
「今学期は“安心”を大切にする」など、自分のクラスに向けた言葉を考えてみましょう。
その一言が、先生の判断を助け、子どもの成長を支えるコンパスになります。
👉 あなたのクラスの“戦略”は何ですか?
👉 来週からの学期に向けて、一言の学期目標を立ててみませんか?
次回予告
次回の記事では「学級経営案の作り方」を具体的に解説します。
「学期目標をどう立てるか」「行事と学習をどう結びつけるか」「コア活動をどう選ぶか」など、すぐに使えるステップを紹介します。

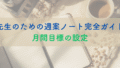

コメント